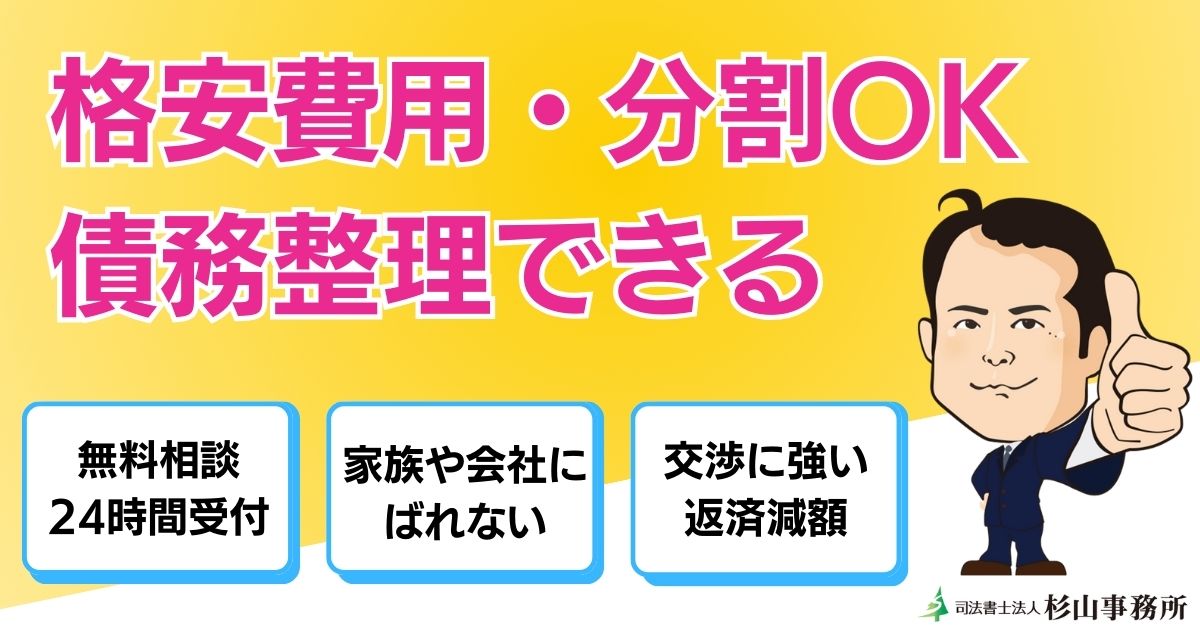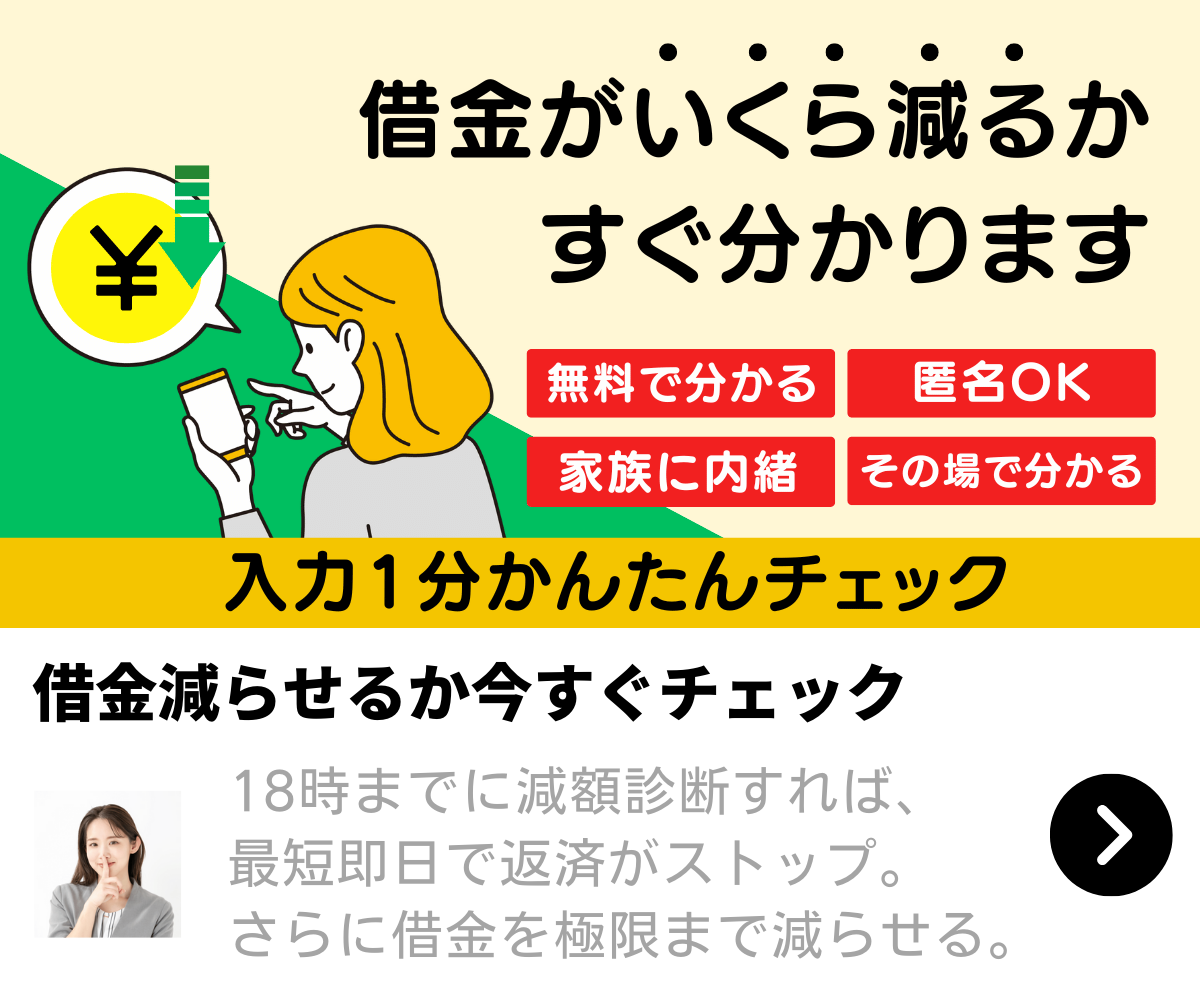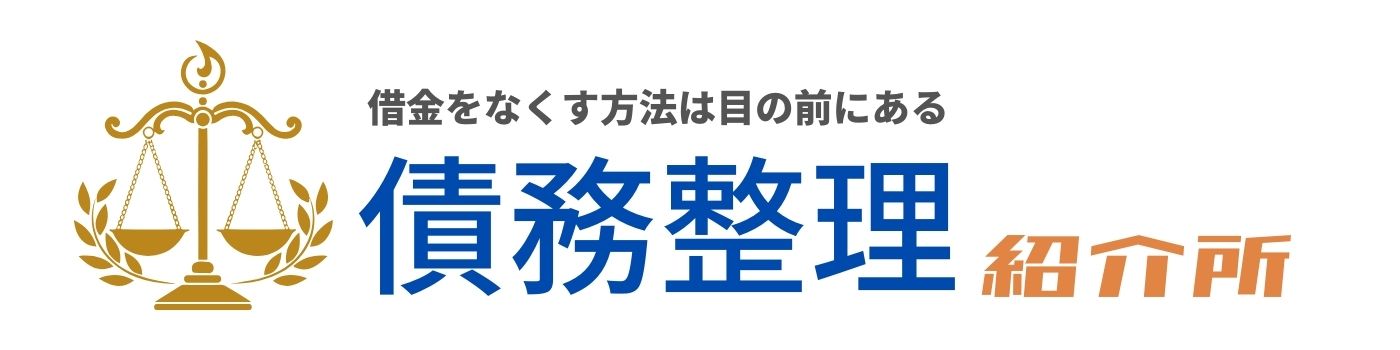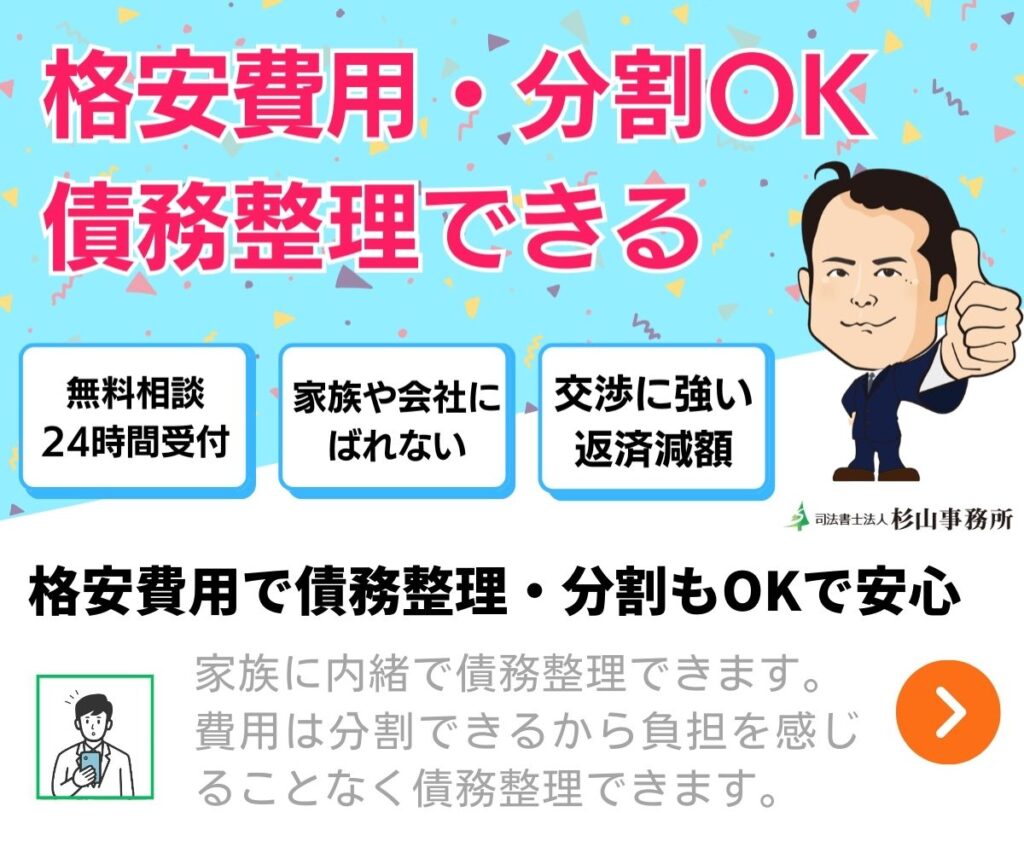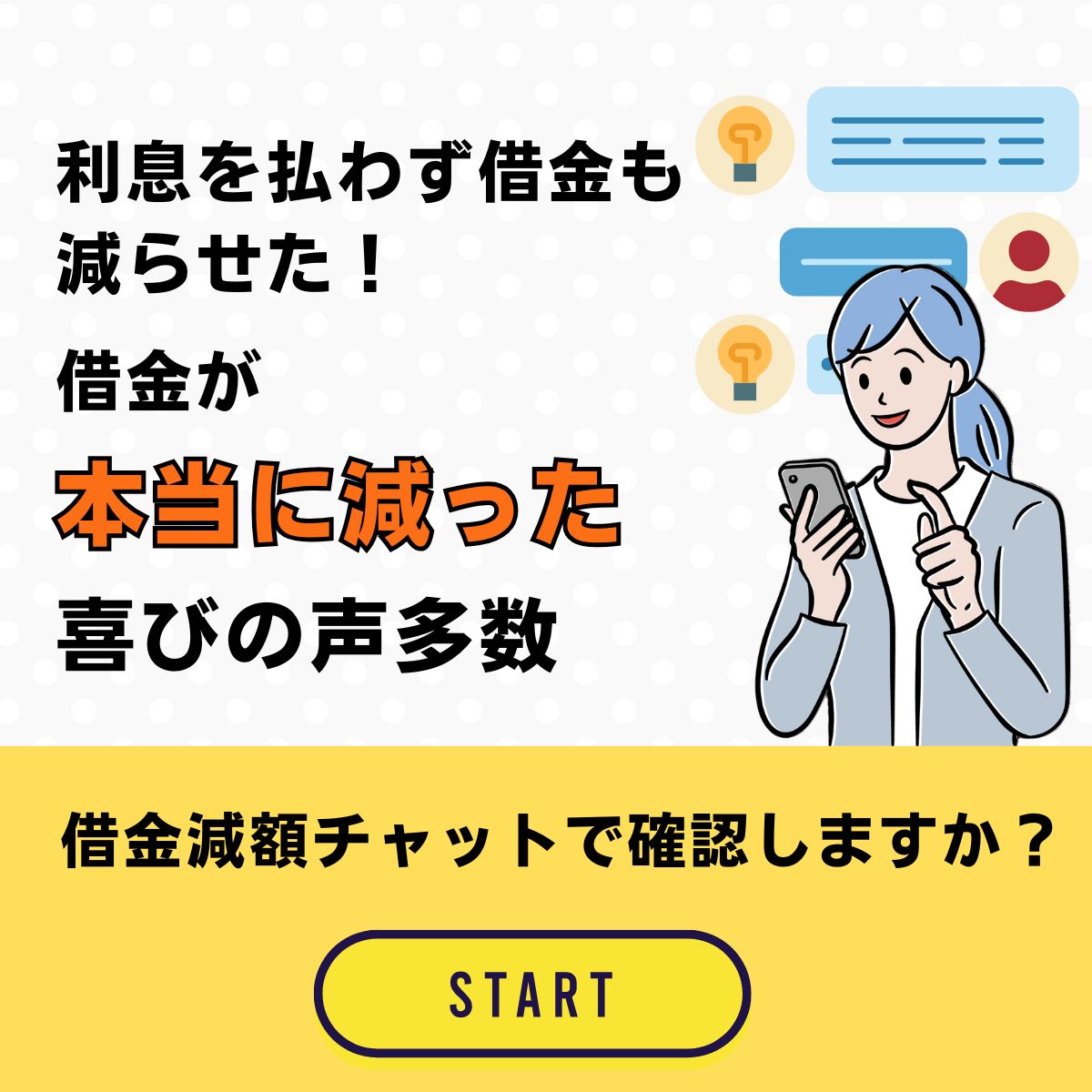任意整理の弁護士費用は?知恵袋の質問から相場や内訳を解説
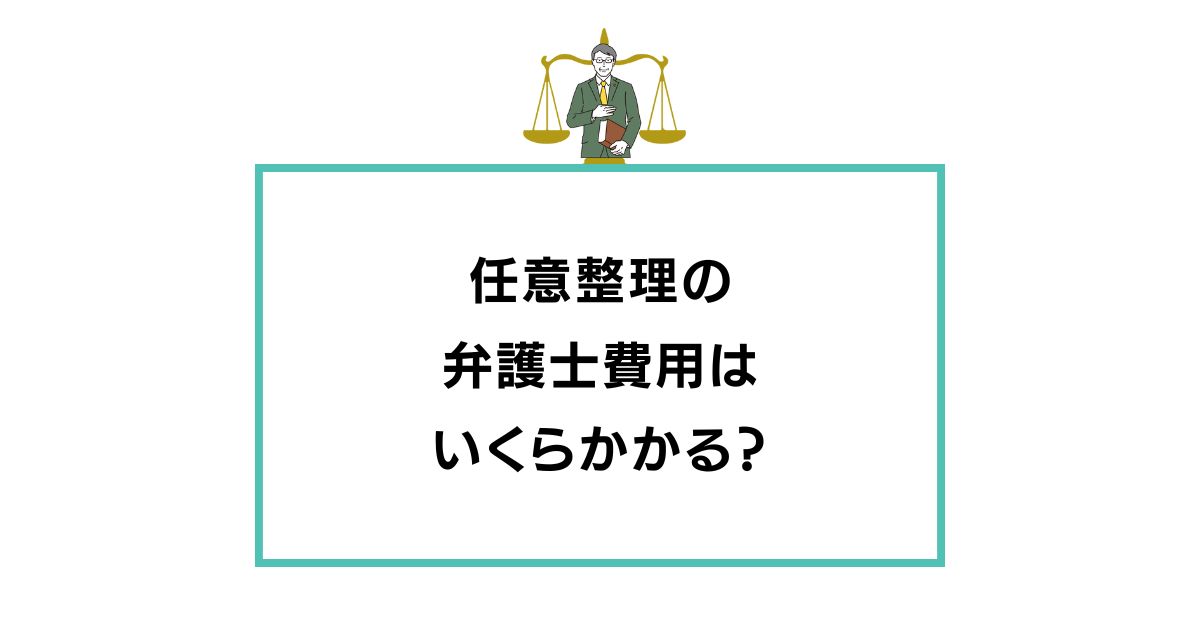
任意整理の弁護士費用は一般的に1社あたり5万円から15万円程度が相場となっています。多くの事務所は分割支払いができる仕組みを取り入れていますが、費用が高すぎる弁護士事務所に依頼したことで途中で支払えず断念してしまうケースは珍しくありません。
そもそも弁護士よりも司法書士に頼んだ方が費用も抑えながら、しっかり借金の減額ができるケースもあります。

知恵袋によくある質問
任意整理をするとどうなりますか?月々の支払いが大変で(自業自得)任意整理を弁護士法人響に任せようかと思っています。
Yahoo知恵袋より
任意整理にかかる弁護士費用って月々の返済額に含まれているんですか?また、成功報酬金って何ですか?これは完済後に一括で払わなければいけないとか、そういうやつなんですか?
Yahoo知恵袋より
任意整理の弁護士費用はいくらかかる?相場を詳しく解説
任意整理の弁護士費用は、1社あたり5万円から15万円程度が一般的な相場となっています。ただし、これは目安の金額であり、実際の費用は債権者の数や借金額、事案の複雑さによって変動します。
借金問題で悩んでいる方にとって、この費用は決して安くはありませんが、専門家に依頼することで督促や取り立ての心配から解放され、計画的な返済が可能になります。
費用の全体像
弁護士に任意整理を依頼する場合の費用は、大きく分けて以下の3つから構成されています。
| 費用の種類 | 金額の目安 | 説明 |
|---|---|---|
| 着手金 | 1社2~5万円程度 | 依頼時に必要な初期費用 |
| 報酬金 | 解決報酬金:1社2万円以下 | 和解成立時の報酬 |
| 減額報酬金:減額分の10%以下 | 借金減額時の報酬 | |
| 過払い金報酬金:回収額の20~25%以下 | 過払い金回収時の報酬 | |
| 実費 | 数千円~1万円程度 | 郵便切手代などの諸経費 |
これらの費用は、日本弁護士連合会が定めた規定に基づいて設定されているため、極端に高額な請求をされることはありません。法律事務所によっては分割払いにも対応しているので、一括で支払うことが難しい場合でも対応してくれる可能性があります。
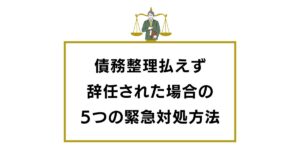
1社あたりの相場金額
任意整理の1社あたりにかかる費用の具体的な内訳について見ていきましょう。基本となる着手金は2万円から5万円が一般的です。これに加えて、債務の減額に成功した場合は減額報酬金として減額された金額の10%程度、過払い金が見つかった場合は回収額の20%程度が加算されます。
例えば、
100万円の借金が60万円に減額された場合、減額報酬金は4万円(40万円の10%)となります。
このように、最終的な費用は交渉結果によって変動する仕組みになっています。
債権者数による費用変動
任意整理の総額は、債権者(借入先)の数が増えるほど費用も比例して高くなります。例えば、3社から借り入れがある場合、着手金だけでも15万円程度必要になることもあります。
ただし、多くの法律事務所では分割払いに対応しているほか、債権者への支払いが一時的にストップするため、その間に費用を準備することも可能です。
また、過払い金が発見された場合は、その返還金を費用に充てることもできます。このように、一見高額に見える費用も、様々な支払い方法や工夫によって対応することが可能です。
任意整理の弁護士費用の内訳を徹底解説
任意整理の弁護士費用は、着手金、報酬金、実費の3つに分類されます。これらの費用は日本弁護士連合会によって上限が定められており、依頼者が不当に高額な請求を受けることがないよう保護されています。
着手金について
着手金は任意整理を依頼する際に最初に支払う費用で、1社あたり2万円から5万円程度が相場となっています。この金額は依頼者と弁護士の間で結ぶ委任契約時に発生し、手続きの成否に関わらず返金されないのが一般的です。
ただし、多くの法律事務所では初回相談料を無料にしているほか、着手金の分割払いにも対応しています。着手金を支払うことで、弁護士は債権者に対して受任通知を送付し、それ以降の督促や取り立てを止めることができるようになります。

着手金を支払う前に受任通知を出してくれる事務所もあるよ
報酬金の種類と金額
報酬金は手続きの成功度合いによって発生する費用です。
主に解決報酬金、減額報酬金、過払金報酬金の3つがあります。
| 報酬金の種類 | 上限額 | 説明 |
|---|---|---|
| 解決報酬金 | 1社2万円以下 | 債権者との和解が成立した場合に発生 |
| 減額報酬金 | 減額分の10%以下 | 借金が減額された場合に発生 |
| 過払い金報酬金 | 回収額の20%以下(訴訟外) 25%以下(訴訟) | 過払い金が回収できた場合に発生 |
これらの報酬金は、実際に成果が出た場合にのみ発生するため、依頼者にとっても分かりやすい費用体系となっています。例えば、100万円の借金が70万円に減額された場合、減額報酬金は30万円(減額分)の10%である3万円となります。
実費・諸経費の内容
実費や諸経費は、任意整理の手続きを進める上で必要となる実務的な費用です。主な内訳は郵便切手代や送金手数料で、金額は数千円から1万円程度です。具体的には、債権者への通知を送る際の郵便代や、和解後の返済金を弁護士事務所経由で支払う場合の振込手数料などが含まれます。
これらの費用は、実際にかかった金額のみを請求されるのが一般的で、不当に上乗せされることはありません。また、多くの法律事務所では見積もりの段階で概算額を提示してくれるため、事前に必要な金額を把握することができます。
任意整理の費用を抑えるポイント
任意整理の費用は決して安くはありませんが、いくつかの方法を組み合わせることで、費用負担を抑えることが可能です。ここでは具体的な費用節約のポイントについて解説していきます。
複数の事務所で見積もりを取る
弁護士事務所によって費用設定は異なるため、**必ず複数の事務所から見積もりを取ることをおすすめ**します。見積もりを比較する際は、単純な金額だけでなく、以下の点にも注目しましょう: – 着手金の金額と分割払いの可否 – 報酬金の計算方法と上限額 – 追加で発生する可能性のある諸経費 – 見積もり内容の説明の丁寧さ – 事務所の対応の親切さ 特に見積もり時の説明が不明確な事務所や、極端に安い金額を提示する事務所は避けたほうが無難です。透明性の高い費用説明をしてくれる事務所を選びましょう。
司法書士に依頼する
借金が1社あたり140万円以下の場合は、司法書士への依頼も検討できます。司法書士の費用は一般的に弁護士よりも安価で、1社あたり着手金が2~3万円程度です。
ただし、司法書士では対応できる業務に制限があり、裁判所での代理人になれないなどの制限があります。そのため、複雑な案件や借金額が高額な(1社あたり140万を超える)場合は、弁護士への依頼をおすすめします。
費用の分割払いを活用する
現在では多くの法律事務所が分割払いに対応しています。一般的な分割払いの期間は3~6回が多く、月々の支払額を抑えることができます。また、弁護士に依頼すると債権者からの督促が止まるため、その分の支払いを弁護士費用に回すことも可能です。分割払いの条件は事務所によって異なりますので、以下の点を確認しましょう
現在では多くの法律事務所が分割払いに対応しています。一般的な分割払いの期間は3~6回が多く、月々の支払額を抑えることができます。また、弁護士に依頼すると債権者からの督促が止まるため、その分の支払いを弁護士費用に回すことも可能です。
弁護士事務所を見るチェックポイント
| 確認項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 分割回数 | 3回~6回が一般的 |
| 手数料 | 追加費用の有無 |
| 支払方法 | 振込・引き落としなど |
| 延滞時の対応 | 柔軟な対応が可能か |
法テラスの制度を利用する
経済的に余裕がない方は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用することができます。この制度では、月収や預貯金が一定基準以下の方を対象に、弁護士費用の立替えを行っています。立て替えられた費用は、月額5,000円程度からの分割で返済できます。
また、生活保護を受給している場合は、立替金の返済が猶予されたり、免除されたりする場合もあります。利用には収入などの条件がありますが、費用面で困っている方は積極的に検討する価値のある制度です。